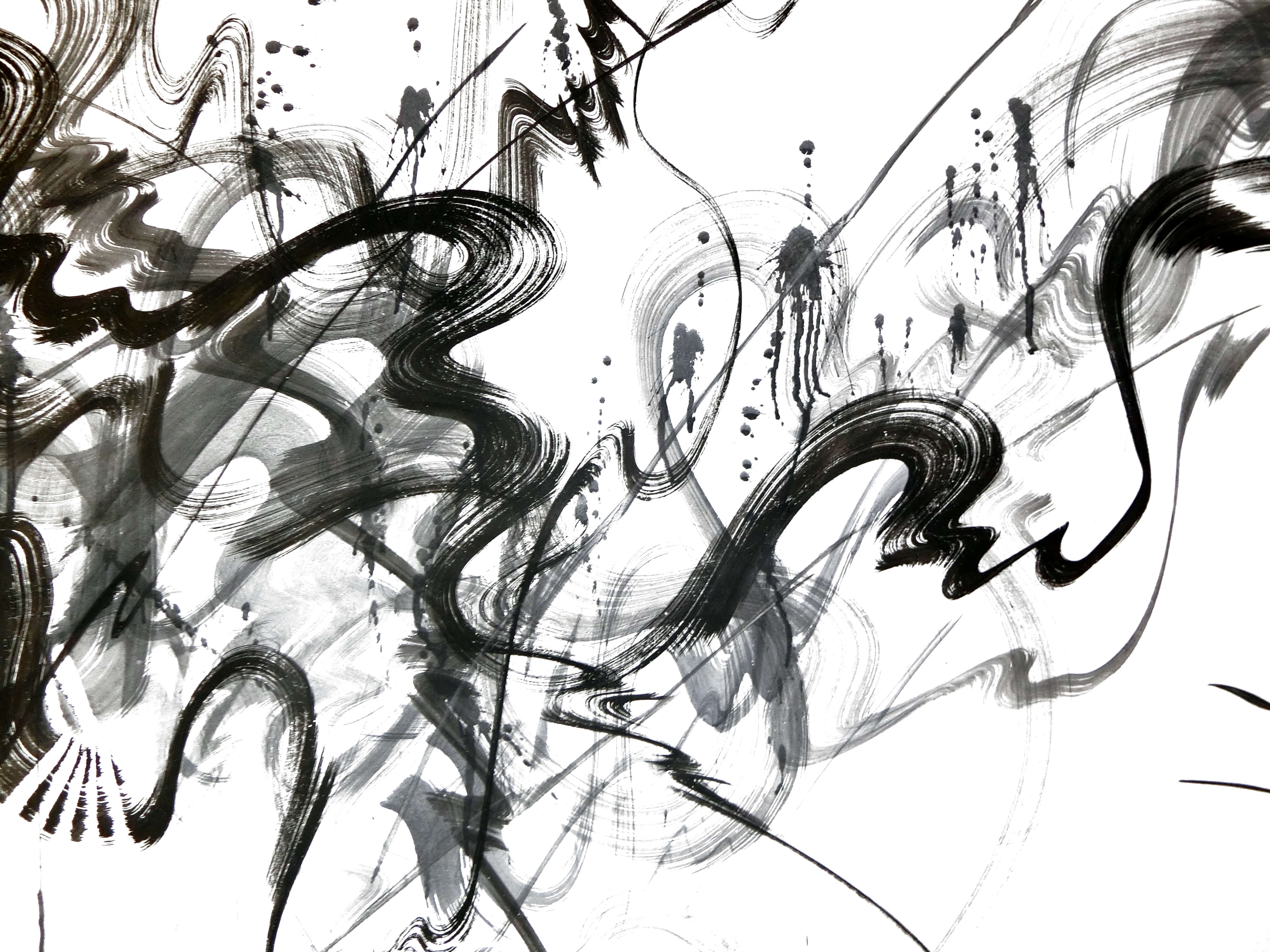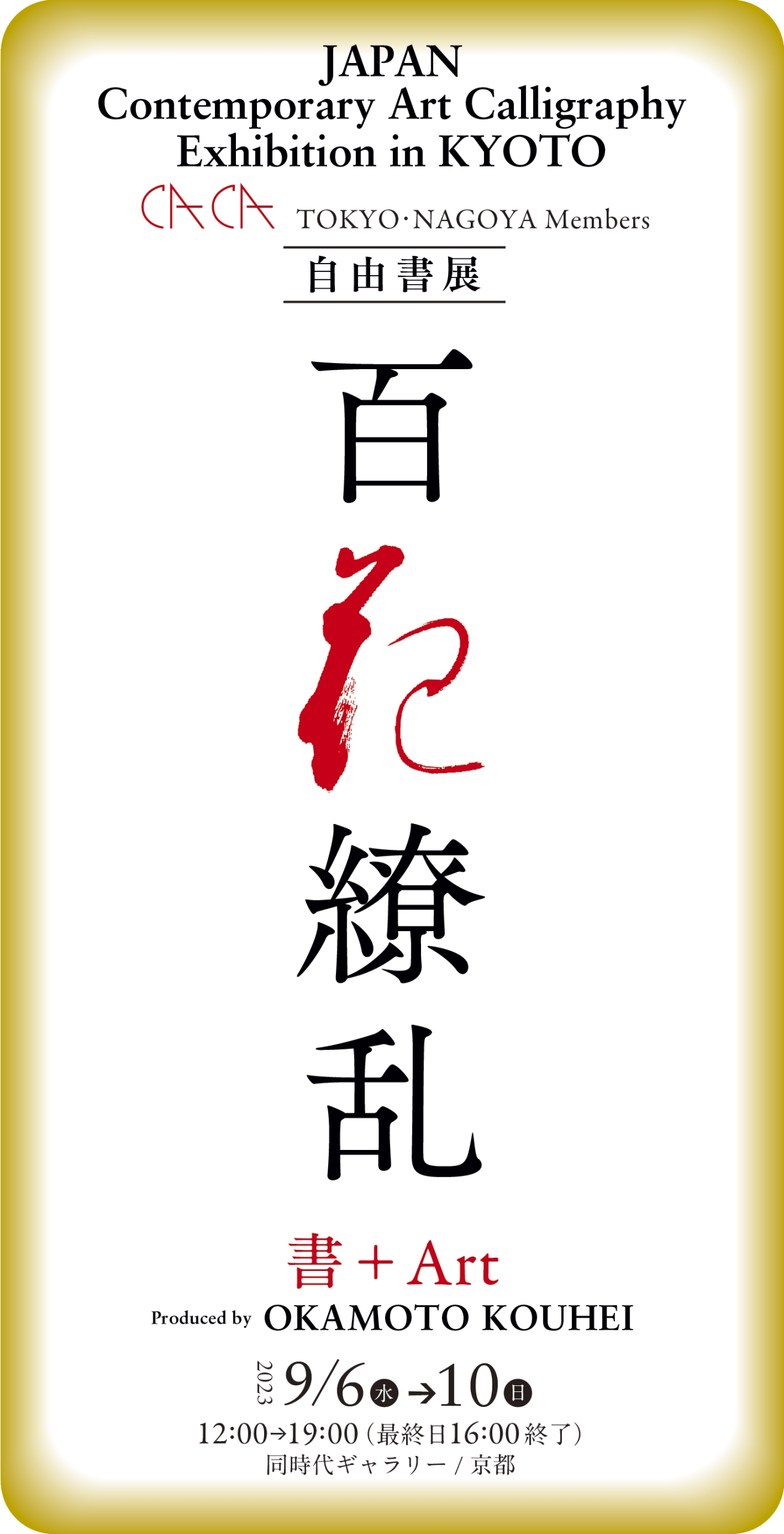
【会期】2023年9月6日(水)〜10日(日)
【時間】12:00〜19:00(最終日16:00まで)
【主催】CACA現代アート書作家協会/Contemporary Art Calligraphers Association
Exhibition Dates: September 6th (Wednesday) to September 10th (Sunday) 12:00 PM to 7:00 PM (Last day ends at 4:00 PM)
【ギャラリートーク】(無料)9月9日(土)14:00〜
特別顧問 岡本光平「書を取り巻く七不思議」
【併設・即売展】
★アートパネル・インテリア作品
★アート・トートバッグ作品
★アート・カジュアルグッズ作品
◆篆刻ライブ(有料)
◆Tシャツライブ(有料)
■Gallery Talk (Free Admission) Special Advisor of CACA: OKAMOTO KOUHEI- "The Seven Wonders Surrounding Calligraphy"
Date: September 9th (Saturday) Time: 2:00 PM
■Concurrent Sales of Art Goods
★ Art Panels and Interior Works
★ Art Tote Bags
★ Various Art Casual Goods
Moreover...
● On the Spot Seal Engraving (Fee-charging)
● On the Spot T-Shirt Brush Writing/Printing (Fee-charging)
京都・同時代ギャラリー
Venue: Kyoto・Dōjidai Gallery
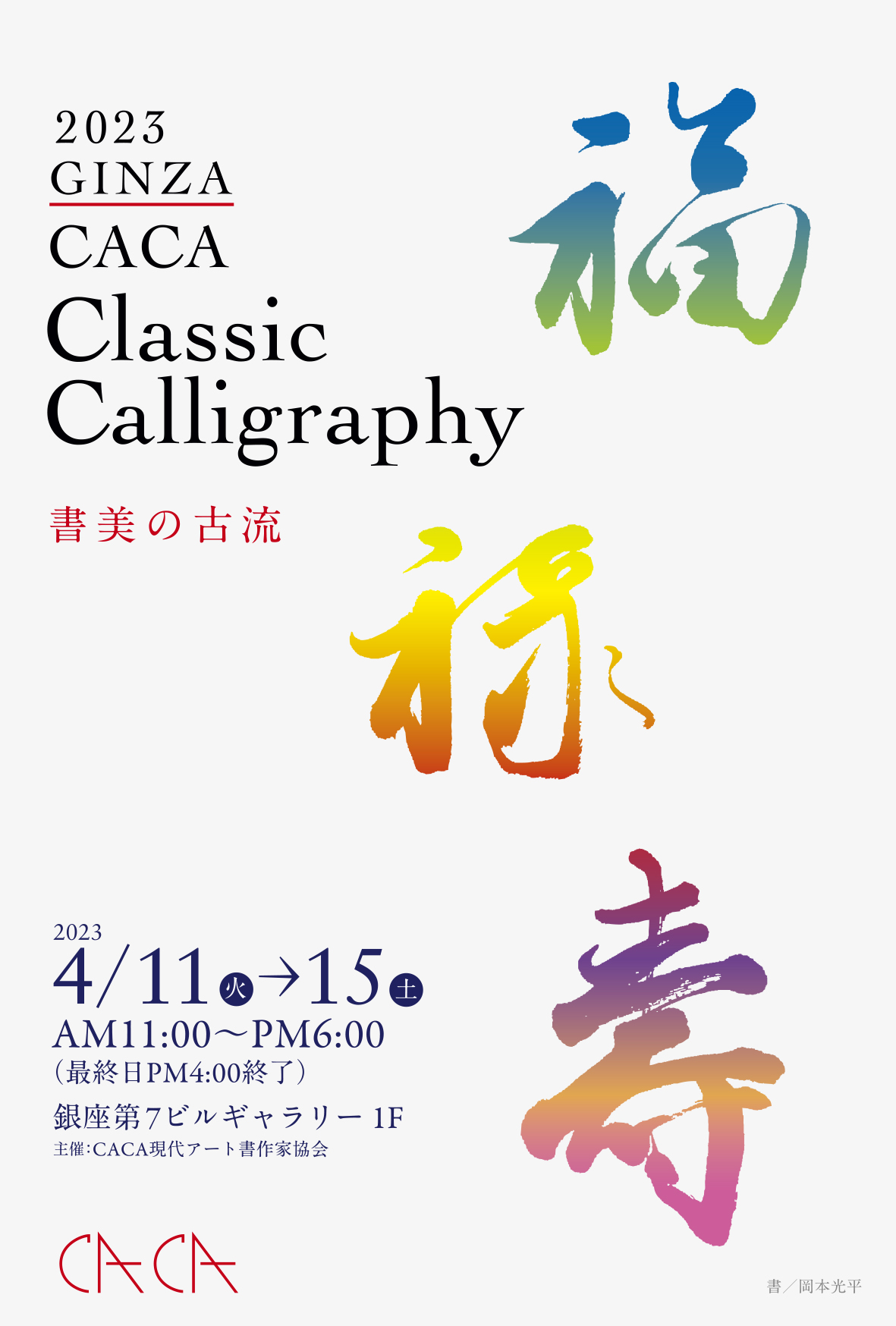
2023年 4月11日(火)→15日(土)
11:00〜18:00(最終日16:00終了)
*入場無料
銀座第7ビルギャラリー 1F
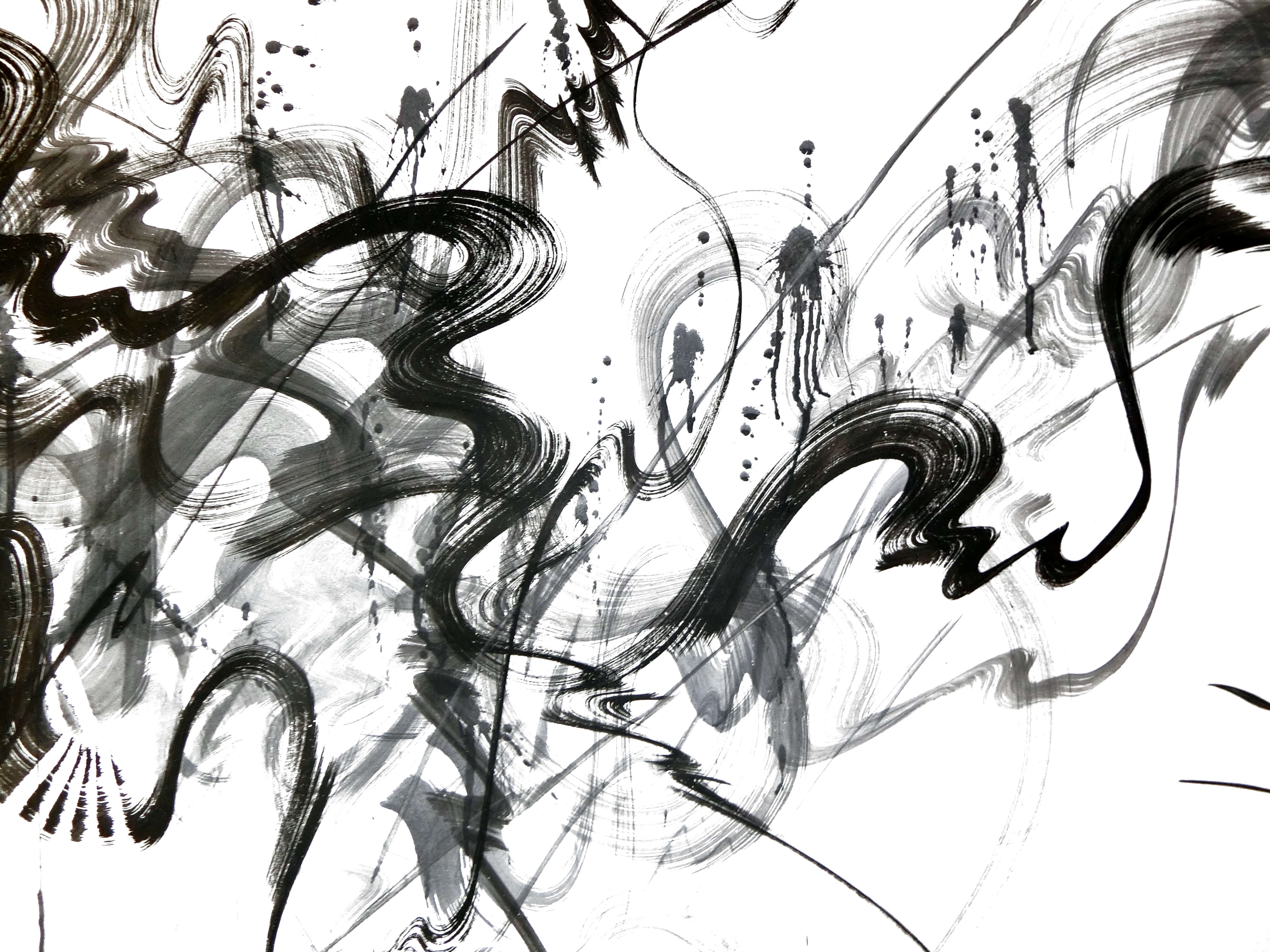
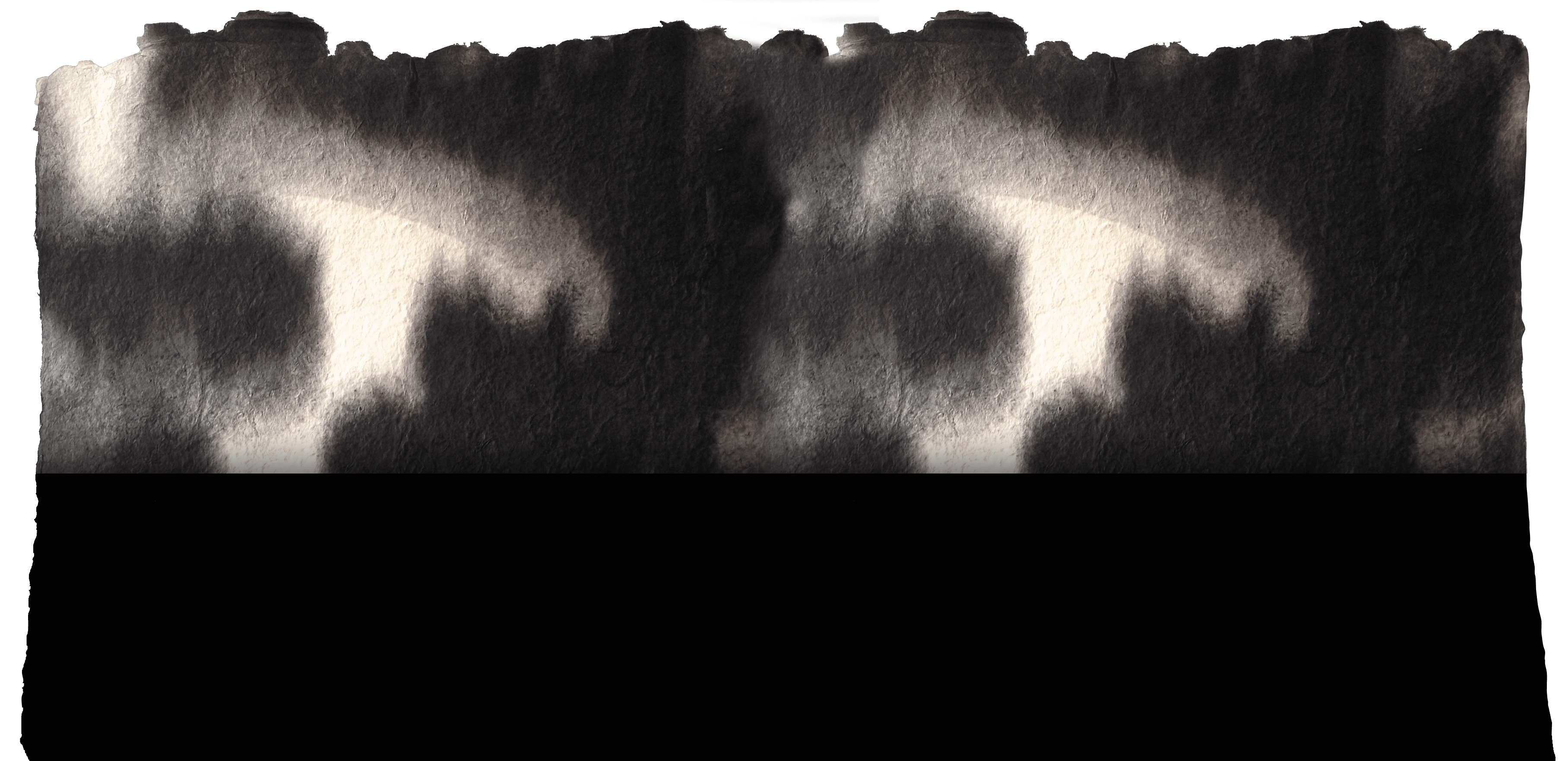
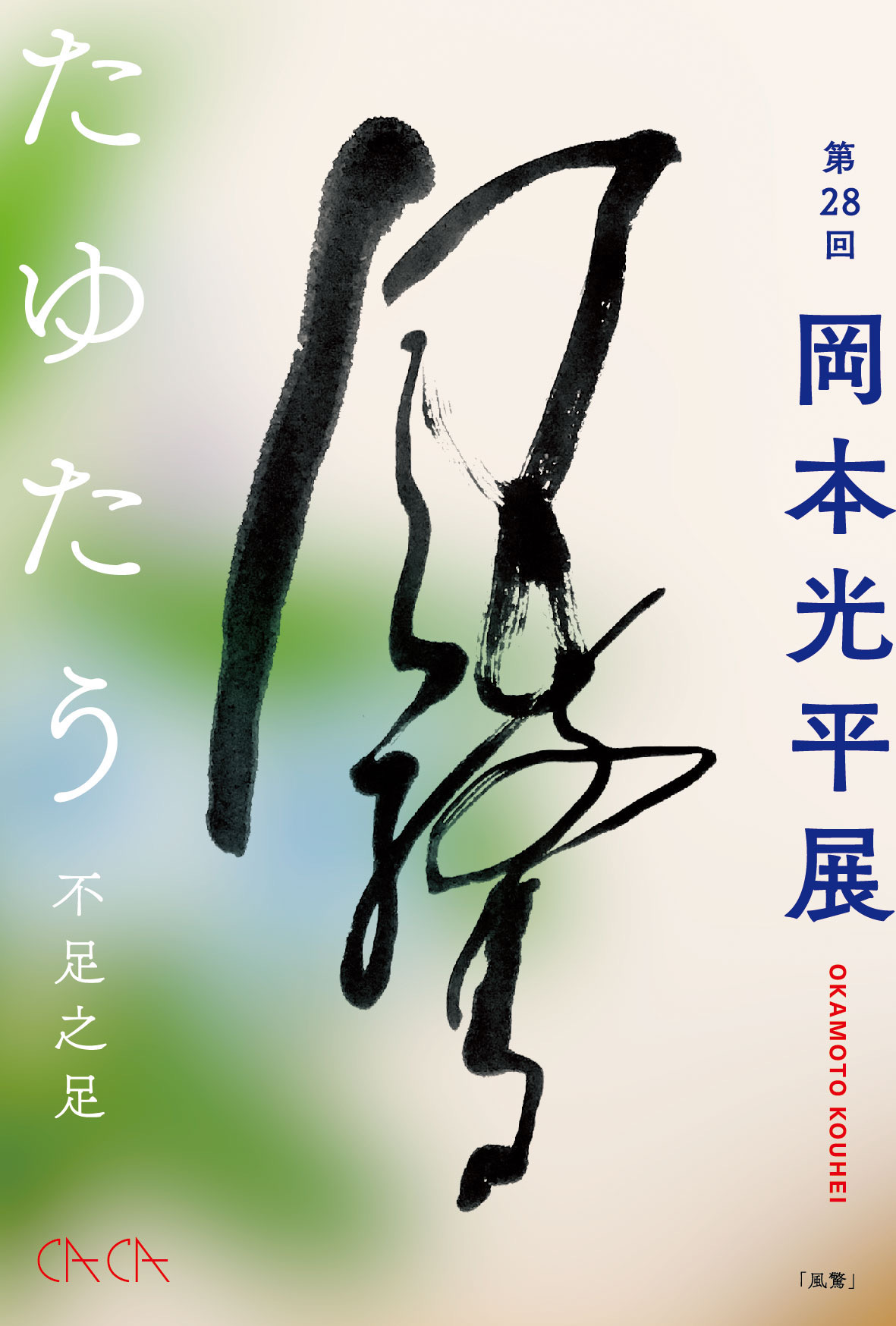
【会期】2024年3月29日(金)〜4月7日(日)12:00~18:00(最終日16:00終了)
●オープニングパーティー 3月29日(金)16:00〜17:30
●岡本光平/揮毫ライブ(有料)
*3月29日(金)~31日(日)
*4月4日(木)~6日(土)
13:00~18:00
*Tシャツ、スカーフなどの依頼をお待ち込みいただき、お好きな文言をリクエストでお書きします。衣類以外もOK。
*4月1日(月)~3日(水)は作家不在につきライブはありません。
●「楽童庵」製作の新作手漉き紙を即売します。
東京・下井草/ギャラリー五峯
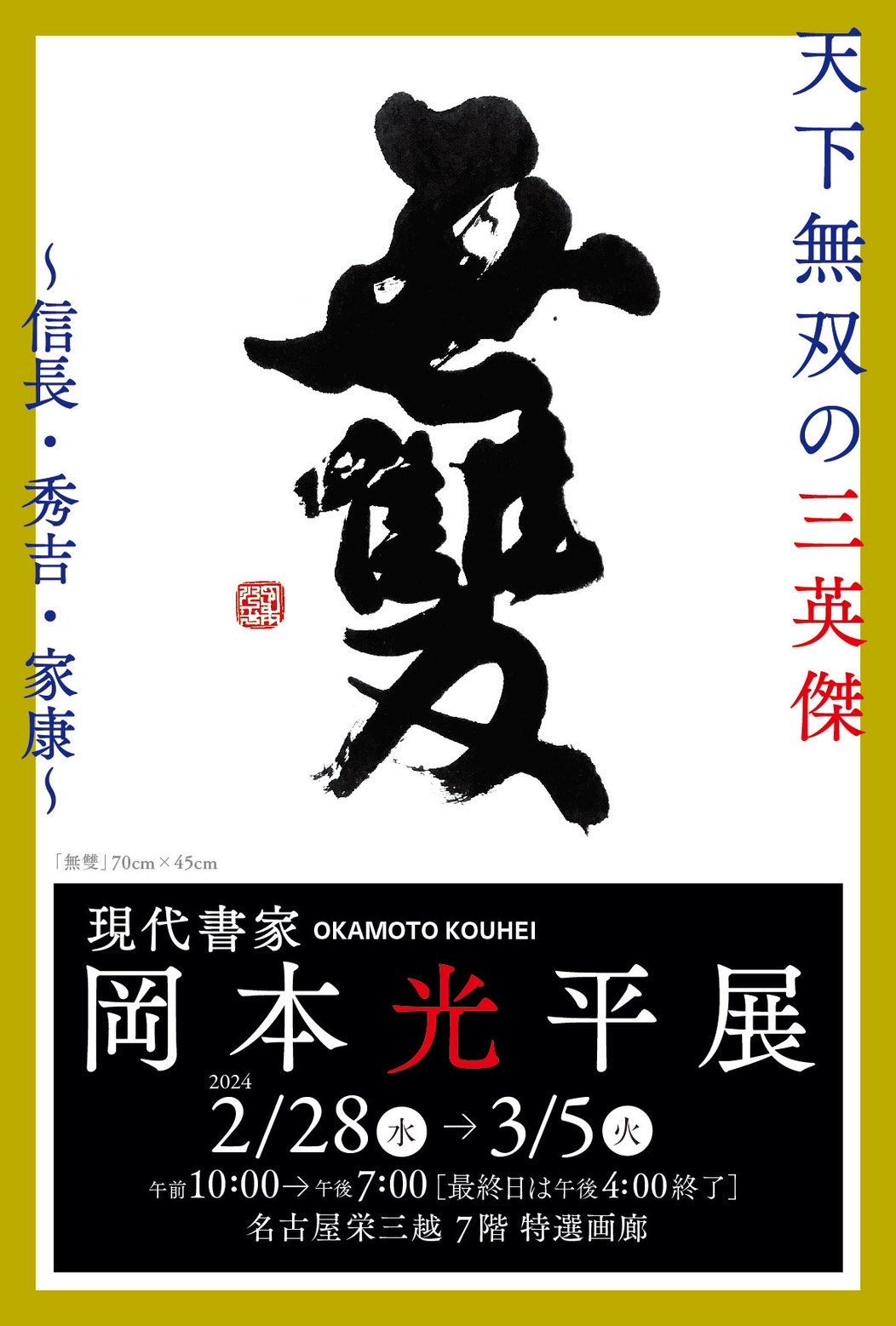
【会期】2024年2月28日(水)→3月5日(火)
【時間】10:00~19:00〈最終日は16:00終了〉
● 書のリクエスト・ライブ
2月28日(水)→3月4日(月) 13:00~18:00
(有料/最終日とギャラリートーク時間を除く)
●ギャラリートーク
「三英傑の足跡を訪ねて」
3月3日(日) 14:00~15:00
名古屋栄三越7階 特選画廊
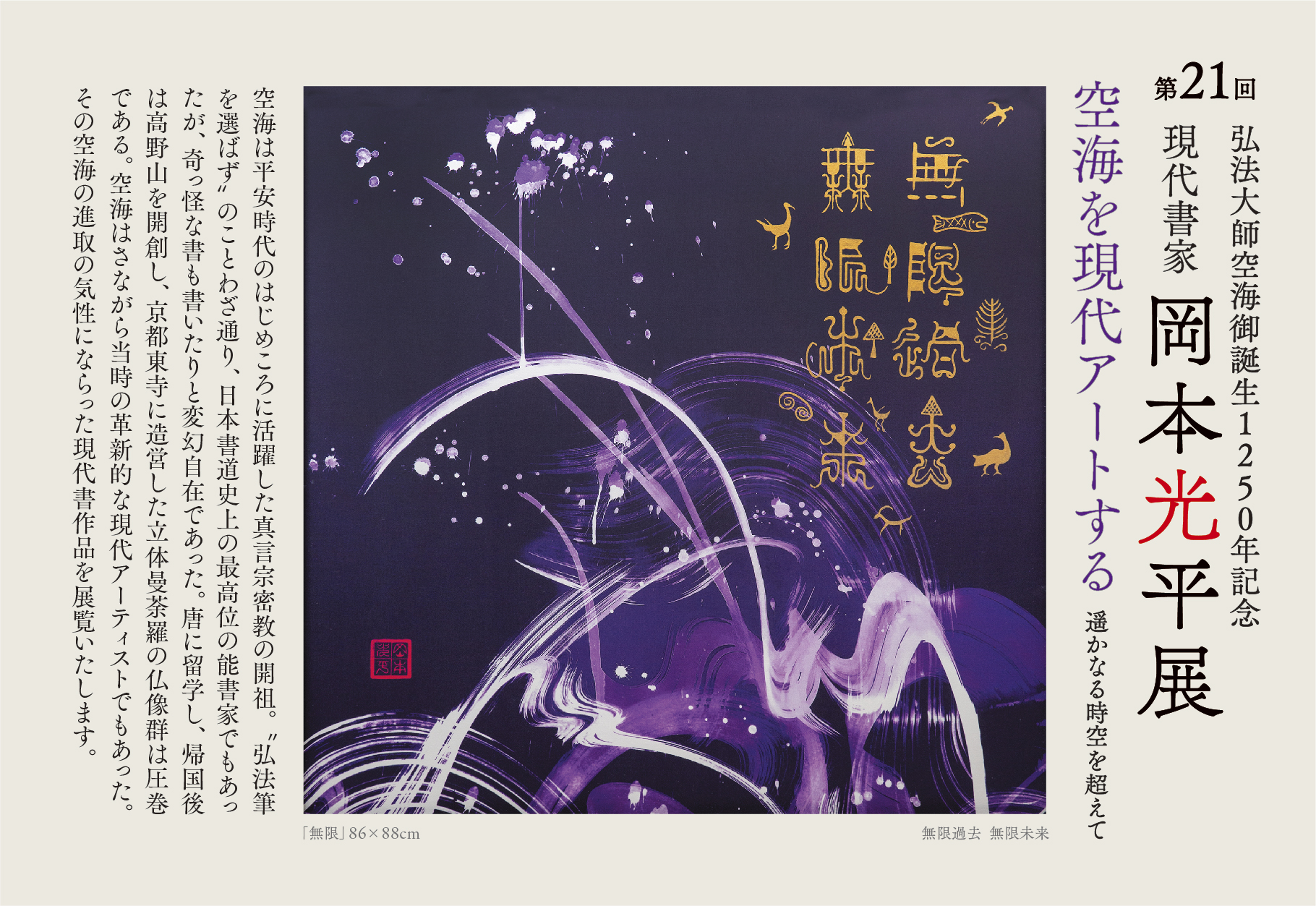
【会期】2023年12月14日(水)→12月20日(水)
【時間】10:00~19:30〈最終日16:30閉場〉
●ギャラリートーク
「書から見た空海の人間像」
12月17日(日)14:00~15:00
●書のリクエストライブ(有料)
12月14日(木)→17日(日)13:00〜18:00 <17日(日)はトーク時間を除く>
*リクエストに応じて、色紙、表札、掛軸、看板、ロゴなどあらゆる書体で、有料にてお書きいたします。
仙台・藤崎本館6階 美術画廊

2024年1月17日(水)~21(日) 最終日16時終了
営業時間11時→19時
※作家は13時→16時まで在廊します
書のインテリア作品、カレンダー、ミニ額、トートバッグ、皮小物入れなど
ガレリアオリザ (ミントカフェ内)
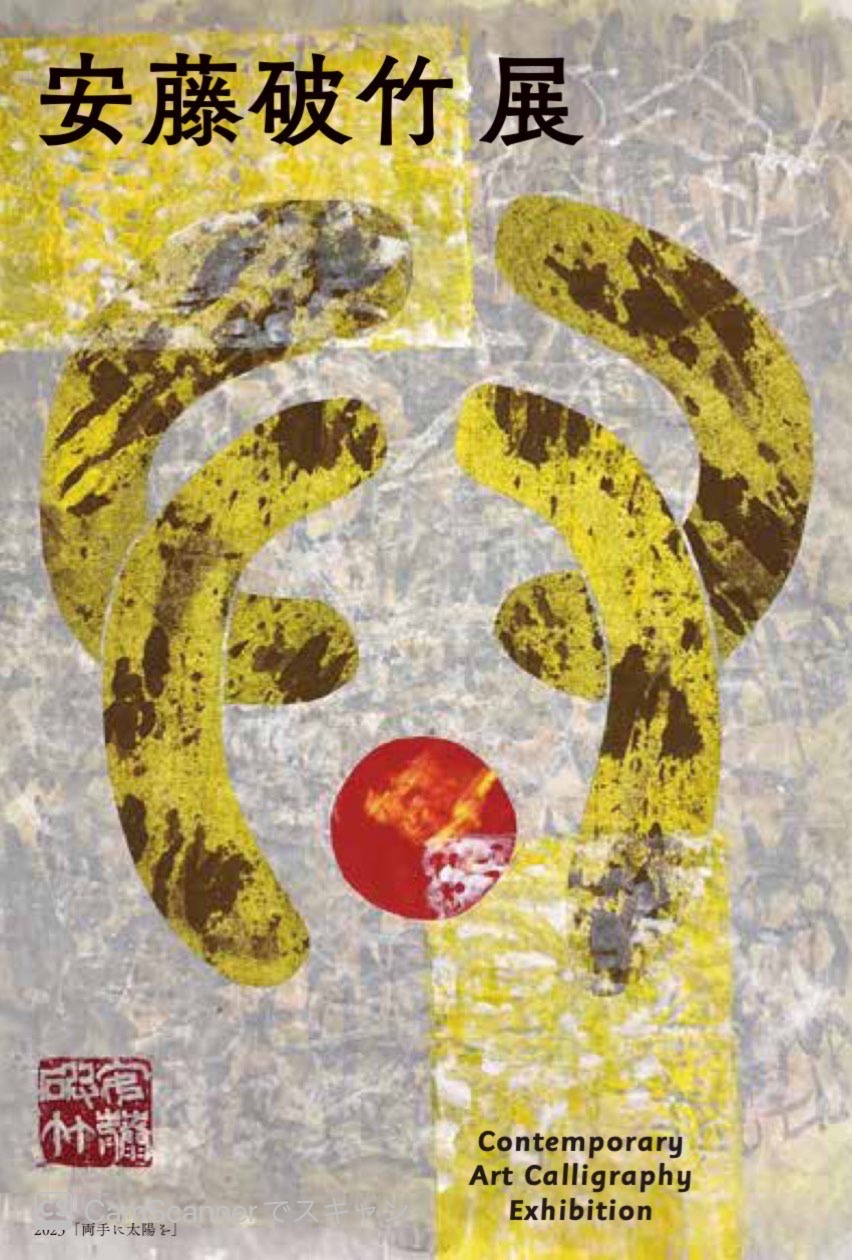
2023年9月29日(金)→10月4日(水)
11:00→18:00(最終日16:00まで)
ギャラリー古島

CACA創立5周年を記念し、横浜、名古屋、京都の巡回展にあたって制作した作品集です。 特別顧問岡本光平による「書アート」とはの論考をはじめ、会員42名の書アート作品を見開きで紹介しています。

A4判/128ページ/フルカラー
PUR並製本/販売価格3,000 円
空海筆による「灌頂記」をはじめ、空海研究をライフワークにしてきた特別顧問・岡本光平による、空海の書の解体。会員20名による原本と臨書作品を見開きで紹介する作品集。展覧会に併せて、毎年発行しています。
A4判/96ページ/モノクロ 並製本/販売価格2,000円
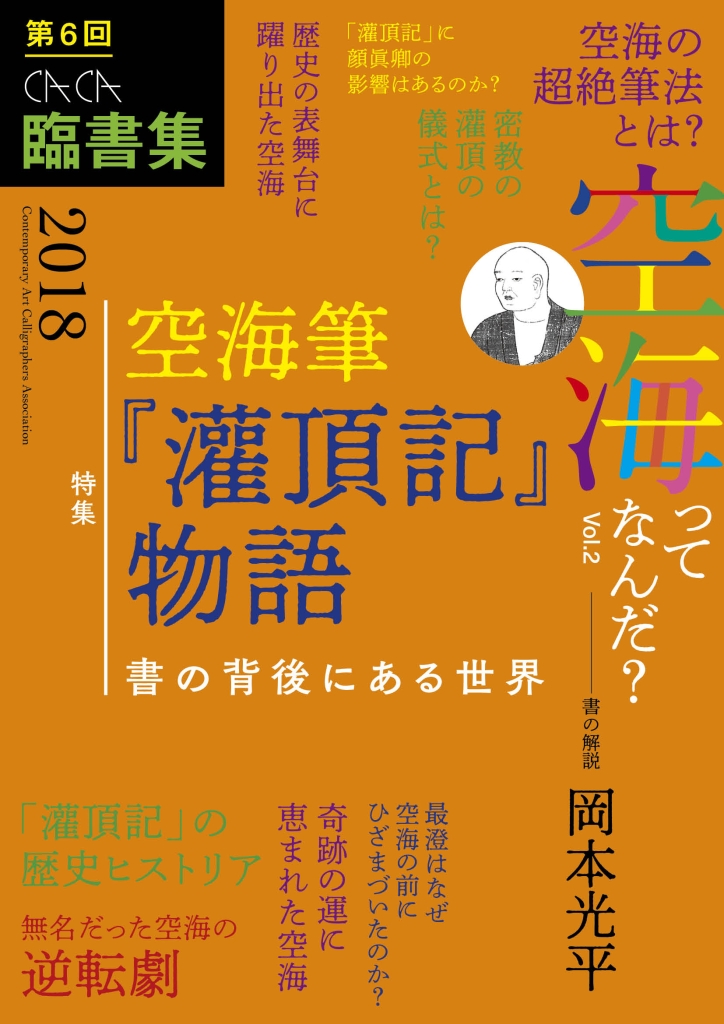


展覧会にあわせて制作している、特別顧問・岡本光平デザインによるTシャツ、トートバッグなどの書アートグッズです